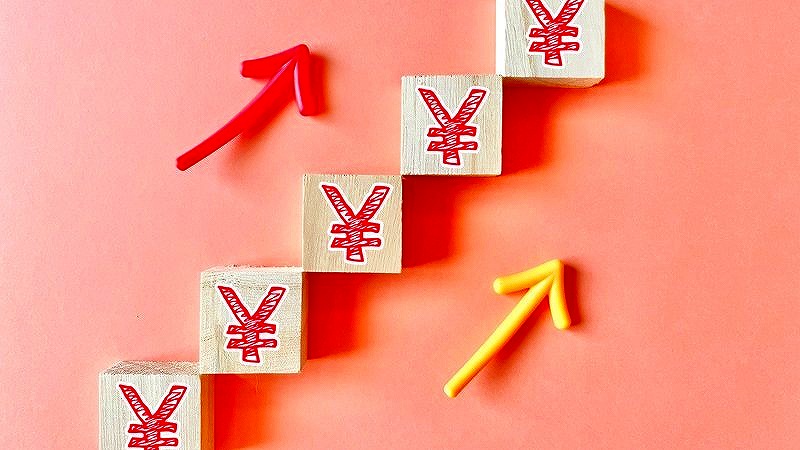2024年から新NISAが始まりました。
なので、インデックス投資もほんの少しだけ注目され始めています。
自分の周囲でも、投資を始めた人がいます。
まあ、資産形成するのであれば始めるのは全然アリだとは思います。
とは言え、絶対にお金が増えるとは言い切れないのが辛いところですけどね。
ただ、インデックス投資の購入方法は自動積立だけではありません。
ということで、今回は「個人的には自動積立よりノーセルリバランスの方が好き」を書いていきます。
ノーセルリバランスとは?

ノーセルリバランスとは、簡単に言うと売らずにリバランスすることです。
要は、買うだけでリバランスします。
例えば、資産AとBに10万円ずつ投資して50%ずつの割合に設定したとします。
| 資産 | 評価額 | 割合 |
| 資産A | 10万円 | 50% |
| 資産B | 10万円 | 50% |
そのまま放置して、1年後に資産Aが12万円、資産Bが8万円になったとします。
| 資産 | 評価額 | 割合 |
| 資産A | 12万円 | 60% |
| 資産B | 8万円 | 40% |
これを10万円の追加投資でノーセルリバランスすると、次のようになります。
| 資産 | 評価額 | 割合 | 投資額 | 合計金額 | 投資後の割合 |
| 資産A | 12万円 | 60% | 3万円 | 15万円 | 50% |
| 資産B | 8万円 | 40% | 7万円 | 15万円 | 50% |
このように、買うだけで投資後の割合が50%ずつになるように調整します。
割合の減った資産を多く買える

ノーセルリバランスのメリットは、割合の減った資産を多く買えることです。
例えば、資産A~Dに10万円ずつ投資して25%ずつの割合にしたとします。
| 資産 | 評価額 | 割合 |
| 資産A | 10万円 | 25% |
| 資産B | 10万円 | 25% |
| 資産C | 10万円 | 25% |
| 資産D | 10万円 | 25% |
そのまま放置して、1年後に資産Aが4万円、資産B~Dが12万円になったとします。
| 資産 | 評価額 | 割合 |
| 資産A | 4万円 | 10% |
| 資産B | 12万円 | 30% |
| 資産C | 12万円 | 30% |
| 資産D | 12万円 | 30% |
これを20万円の追加投資でノーセルリバランスすると、次のようになります。
| 資産 | 評価額 | 割合 | 投資額 | 合計金額 | 投資後の割合 |
| 資産A | 4万円 | 10% | 11万円 | 15万円 | 25% |
| 資産B | 12万円 | 30% | 3万円 | 15万円 | 25% |
| 資産C | 12万円 | 30% | 3万円 | 15万円 | 25% |
| 資産D | 12万円 | 30% | 3万円 | 15万円 | 25% |
このように、「割合が減った=相対的に見て安くなった」資産Aを多く買うことになります。
逆に、「割合が増えた=相対的に見て高くなった」資産B~Dは少なめに買うことになります。
もし仮に、資産A~Dに単純に5万円ずつ自動積立した場合は下記のようになります。
| 資産 | 評価額 | 割合 | 投資額 | 合計金額 | 投資後の割合 |
| 資産A | 4万円 | 10% | 5万円 | 9万円 | 15% |
| 資産B | 12万円 | 30% | 5万円 | 17万円 | 28.3% |
| 資産C | 12万円 | 30% | 5万円 | 17万円 | 28.3% |
| 資産D | 12万円 | 30% | 5万円 | 17万円 | 28.3% |
当然ながら、割合が増えようが減ろうが関係なく5万円ずつ買います。
個人的には、投資の基本は安い時に多めに、高い時に少なめに買うことだと思っています。
なので、ノーセルリバランスの方が好きですね。
自動積立はできない

ただ、ノーセルリバランスで買うと毎回購入金額が変わります。
なので、手動で購入するしかありません。
そこが少々面倒くさいところです。
自動積立設定ができないので、当然ながら新NISAのつみたて投資枠で買うことはできません。
当日買いできる成長投資枠なら、問題なく買えるんですけどね。
計算が面倒くさい

正直言って、ノーセルリバランスは計算が面倒くさいですね。
先ほどの表のような単純なものなら簡単に計算できますが、実際は違います。
1円単位、下手したら小数点の計算になります。
そこでおススメなのは、表計算ソフトを使って自動計算させることです。
今ならGoogleのスプレッドシートが無料で使えますからね。
関数を入れるのは慣れていなければ少々難しいですが、一度作ってしまえばあとは永遠に使えます。
大枠を作って、あとの細かいところは手動で調整するようにすれば、作るのはそれほど難しくはありません。
儲からない場合もある

個人的には、ノーセルリバランスの方が自動積立より好きです。
しかしながら、自動積立の方が儲かるケースも当然あります。
最近で言えば、S&P500と国内債券でノーセルリバランスするような場合ですね。
S&P500は上がり続け、国内債券は下がり続けています。
これを50%ずつの割合にすると、国内債券の割合が下がり続けます。
なので、どうしてもS&P500はあまり買わずに国内債券の方をしこたま買うことになります。
しかし、今のところ国内債券は上がる気配が全くありません。
その場合、何も考えずS&P500に50%の割合で自動積立していた方が儲かります。
ノーセルリバランスは、どちらか一方が上がり続けてはイマイチです。
それよりも、シーソーのような感じでお互い上がったり下がったりした方が効果的です。
ただ、買い方の違いなどはどう買おうとほんの誤差です。(一括投資は別として)
インデックス投資で1番重要なのは、資産配分(アセットアロケーション)をどう決めるかです。
結局のところ、最終的にはそこに落ち着きます。
お金関係の良いサイト

お金関係で、個人的に良いと思うサイトを箇条書きしていきます。
個人的に良いと思う銀行は1つだけです。
- 楽天銀行
楽天証券との口座連携(マネーブリッジ)で金利アップ。銀行は楽天銀行だけで十分。
個人的に良いと思うクレジットカードは3つです。
- 楽天カード
普段使い。基本は楽天ペイにチャージして使う。楽天ポイントが貯まる。年会費無料。 - 三井住友カード(NL)
SBI証券のクレカ積立で使える。年会費無料。クレカ積立以外で年間10万円利用しないとクレカ積立のポイントがもらえないので10万円だけ使う。 - PayPayカード
国民年金納付で1%のポイント還元があるので、その時だけ使う。年会費無料。
個人的に良いと思う証券会社は3つです。
個人的に良いと思うポイントサイトは2つです。
その他、便利だと思うサイトは下記です。
- myINDEX 資産配分ツール
各資産のリターンの確認に便利。インデックス投資をするならマスト。 - 「インデックスファンド」コスト比較ランキング
コストの安いインデックスファンドが分かる。インデックス投資をするならマスト。 - ねんきんネット
自分の年金記録を確認するのに必須。 - マネーフォワードME
自分の資産がどのくらいあるのか分かる。有料なら5つ以上の金融機関を登録できるが、金融機関を整理すれば無料でも十分使える。
お金関係のAmazonランキングは下記です。
ということで、今回は終わりにします。