会社を辞めたら、まずやらなければいけないのが健康保険と年金の手続きです。
これを放っておくと、あとから痛い目にあうこともあるので、早めに動きましょう。
健康保険の手続き
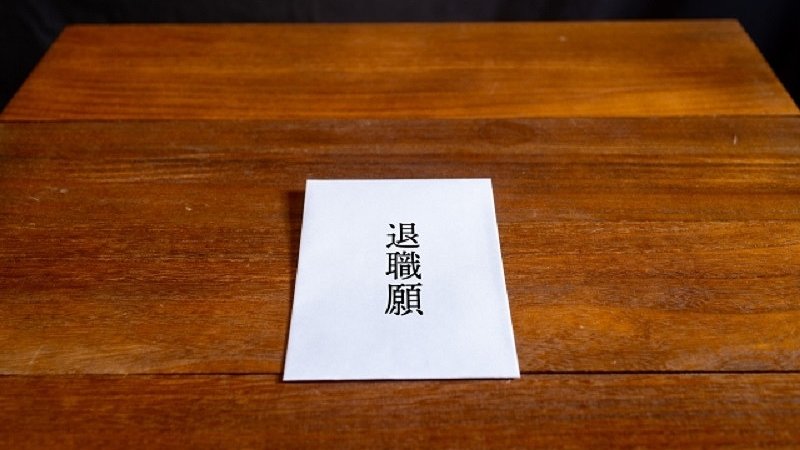
会社員時代は、会社を通じて健康保険に加入していました。
保険料は給料から天引きされ、しかも会社が半分を負担してくれていたので、特に意識することはなかったかもしれません。
でも、退職後はそうはいきません。
保険料は全額自己負担になり、保険の種類も自分で選ぶ必要があります。
健康保険の選択肢は3つ
退職後の健康保険には、次の3つの選択肢があります。
任意継続健康保険
退職前に加入していた健康保険を、最大2年間そのまま継続できる制度。
保険料は原則2年間変わらず、扶養の制度もあるが、会社の補助がなくなるので保険料は2倍に。
国民健康保険
自営業者や無職の人が入る保険。
保険料は前年度の所得を基準に計算され、扶養という概念はなし。
家族の健康保険(被扶養者になる)
配偶者や親などの健康保険の扶養に入る方法。
収入が一定以下であれば保険料負担はなし。
任意継続健康保険を選んだ理由と感想
自分は任意継続を選びました。
理由は会社の総務に「たぶんこっちの方が安い」と言われたから。
だけど実際に届いた納付書を見てびっくり。
月額3万5400円。
会社にいたときの2倍なので当然なんですが、無職状態でこの額はキツいです。
ちなみに手続き自体は簡単。
「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を全国健康保険協会(協会けんぽ)に郵送するだけ。
これは退職時に会社からもらえるはずです。
2年目からの選択肢も考えておく
任意継続は2年間保険料が固定されますが、退職翌年は所得がガクッと落ちる人も多いはず。
そうなると、2年目からは国民健康保険の方が安くなるケースもあります。
実際、自分も2年目は国民健康保険に切り替えて、かなり保険料が安くなりました。
健康保険の切り替えは月単位で行えます。2年目の4月に切り替えると、前年度所得ベースの安い保険料が適用される可能性が高いです。
保険を切り替える際は、空白期間ができないように注意。切り替えの手続きは前月中に済ませるのが安心です。
- 健康保険は退職後、自分で選んで加入する必要あり
- 任意継続は2年まで、保険料は会社時代の2倍
- 所得次第では2年目から国民健康保険の方が安くなることも
国民年金の手続き
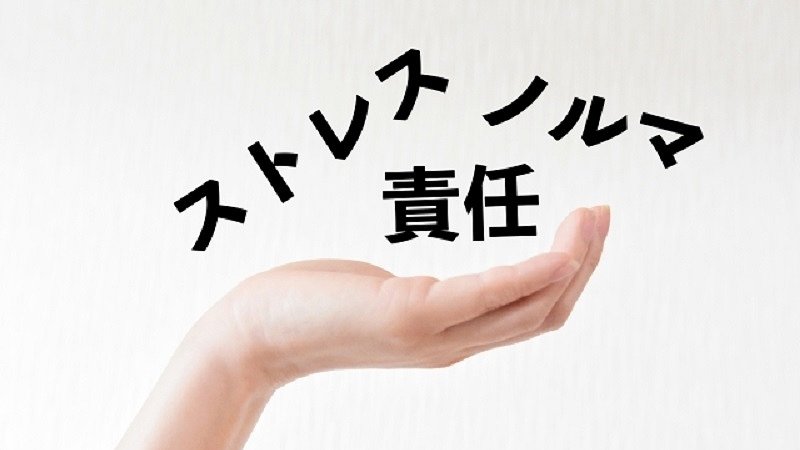
会社にいたときは厚生年金に加入していたはずです。
でも、退職後は厚生年金の資格を失い、国民年金に切り替える必要があります。
これも放置していると未納扱いになるので注意。
手続き方法と必要なもの
手続きは最寄りの年金事務所でできます。
必要なものは以下の3点です。
- 健康保険・厚生年金保険資格喪失確認通知書(会社からもらえる)
- 離職票(または退職証明書)
- 印鑑
すべて揃えたら、年金事務所の窓口に提出するだけでOKです。
2年前納がかなりお得
国民年金は毎月払うだけでなく、前納制度もあります。
なかでも「2年前納」は最も割引率が高くてお得。
自分の場合、クレジットカード払いにして、PayPayカードを使いました。
ポイントもつくので実質さらに割引です。
2年前納をクレカ払いにすると、1万円近く安くなるケースもあります。さらにポイント還元でお得度アップ。
40万円近い金額を一括納付する必要があるので、事前に資金計画を立てておきましょう。
- 国民年金は退職後すぐ切り替えが必要
- 2年前納+クレカ払いが一番お得
- 年金手続きには離職票など会社からもらった書類が必要
付加年金は絶対入った方がいい
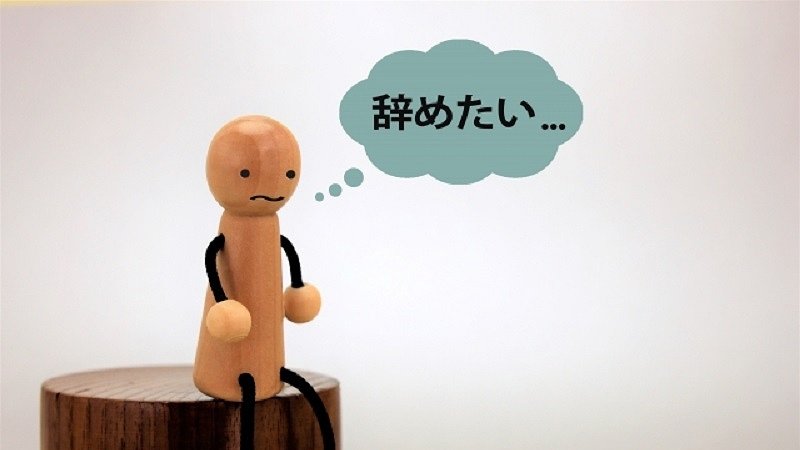
もし国民年金を納めるなら、「付加年金」もセットで入るのがおすすめ。
これは月額400円を上乗せして納付する制度で、将来もらえる年金額が増えます。
どう増えるかというと、「付加年金を納めた年数 × 200円」が、毎年の年金に上乗せされるんです。
つまり2年で元が取れて、そのあとはずっと得。
こんなコスパのいい制度、他にありません。
- 月額400円で将来もらえる年金が増える
- 2年で元が取れて、あとは長生きするほど得
- 国民年金に加入する人は付加年金も申し込もう
年金は「ねんきんネット」で確認しよう
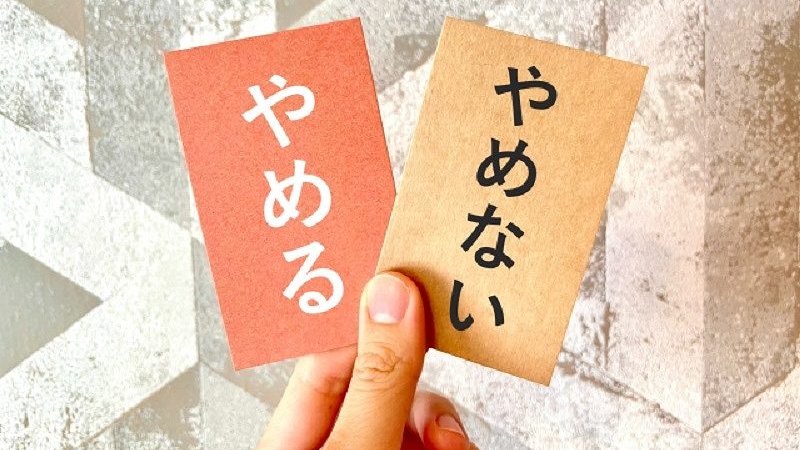
年金の記録って、自分でしっかり把握しておく必要があります。
「ねんきんネット」に登録すれば、スマホやパソコンからいつでも年金記録を確認できます。
登録には基礎年金番号が必要ですが、これは年金手帳や年金通知書などに書かれています。
まだ登録していない人は、今のうちにやっておきましょう。
参考リンク:ねんきんネット
- 年金記録は「ねんきんネット」でいつでも確認可能
- 基礎年金番号があれば誰でも登録できる
- 記録ミスを防ぐためにも、定期的にチェックがおすすめ
まとめ

退職後は、健康保険と年金の手続きを自分でやる必要があります。
難しそうに見えても、実際にやってみると意外と簡単。
ただ、どの保険を選ぶか、どう納付するかで支払額が大きく変わるので、しっかり調べて自分に合った選択をしましょう。
事前に知っていれば、かなりの節約にもつながります。
