iDeCoは、所得控除で節税できるならなるべく使いたい制度です。
自分も2022年から始めています。
iDeCoでの投資は、自分のようなFIRE民にも欠かせませんね。
節税や一時金受け取り時の退職所得控除額が増えるなど、いろいろなメリットがあります。
ということで、今回はFIRE民がiDeCoを使うメリットについて書いていきます。
年間80万円ほど投資できる
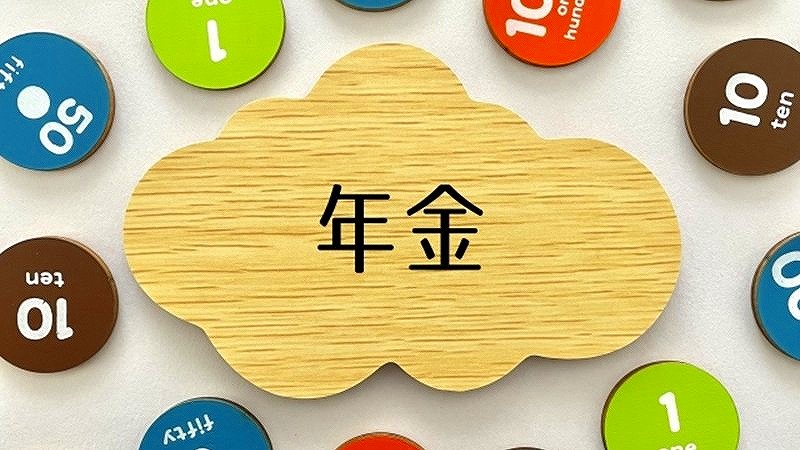
FIRE民は働いていないので、第1号被保険者が多いでしょう。
第1号被保険者の年間拠出限度額は、81万6000円(6万8000円/月)もあります。
サラリーマンなどは年間27万6000円しか投資できないので、かなり差があります。
投資枠は少ないよりも多い方が良いに決まっているので、これは嬉しいですよね。
新NISA(年間投資枠360万円)と合わせれば、年に440万円も投資できます。
こんなに投資できる人はほとんどいないと思いますが…。
最大30万円ほど節税できる
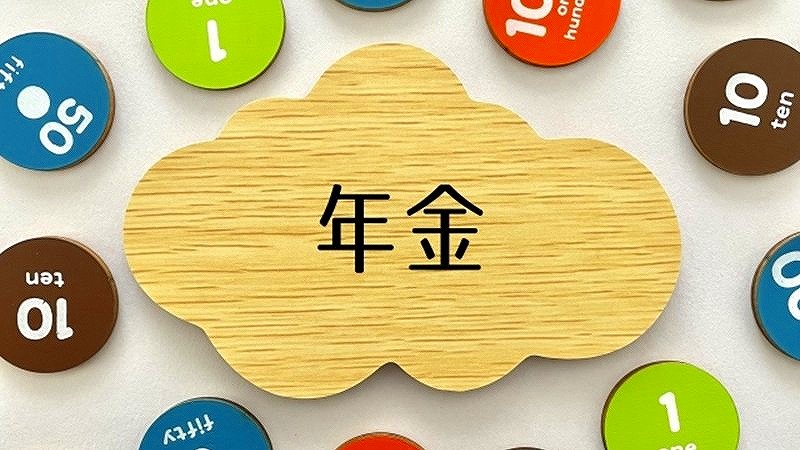
iDeCoで年間80万円ほど投資しておくと、所得控除額は最低でも150万円ほどになります。
他に、所得税の基礎控除(48万円)と国民年金保険料(約20万円)の控除がありますからね。
※国民年金保険料を納付していないとiDeCoで投資できない
この150万円の所得控除額は、他に収入がない場合は特定口座の所得と相殺できます。
なので、特定口座で150万円の所得を出しても税金がかかりません。(源泉徴収されている場合は確定申告で取り戻せる)
要は、新NISA口座で投資しているのと一緒です。
通常では、特定口座で150万円の所得を出すと金融所得課税(20.315%)で約30万円を取られます。
それがチャラになるので、非常にありがたいですよね。
これもiDeCoで年間80万円ほど投資できるおかげです。
150万円の所得を出せるのであれば、元本の2倍に増えた投資信託を300万円取り崩せます。
これだけ取り崩せれば、十分生活の足しになります。(iDeCoの投資に80万円は取られますが)
余っている退職所得控除額を使える
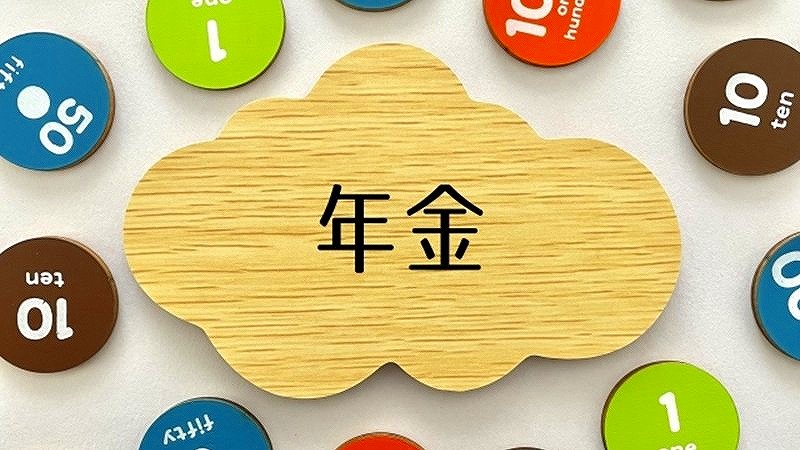
iDeCoを一時金で受け取る時は退職所得となり、退職所得控除が使えます。
退職所得控除額の計算方法は、下記になります。
| 勤続年数(=A) | 退職所得控除額 |
| 20年以下 | 40万円×A(80万円に満たない場合には、80万円) |
| 20年超 | 800万円+70万円×(A-20年) |
上記で計算すると、15年勤続した時の退職所得控除額は600万円です。
仮に早期退職で退職金が200万円しか出なかった場合は、退職所得控除額が400万円余ります。
その400万円を、iDeCoの一時金受け取り時に使うことができます。
※退職後20年以上ならリセットされるようです(詳しく知りたい方はこちら)
これは非常にありがたいですよね。
退職金の安いクソな会社でも、iDeCoの一時金受け取り時にほんの少しだけ役に立つということです。
もちろん、退職所得控除額を超える退職金をもらえる方が嬉しいですが…。
iDeCoの一時金受け取りの際は退職所得の源泉徴収票(コピー)が必要なので、退職金をもらったあとも大事に取っておきましょう。
もし無くした場合は、早急に再発行することをおススメします。(再発行の期限があるかもしれないので。中退共では10年です)
退職所得控除の年数を増やせる
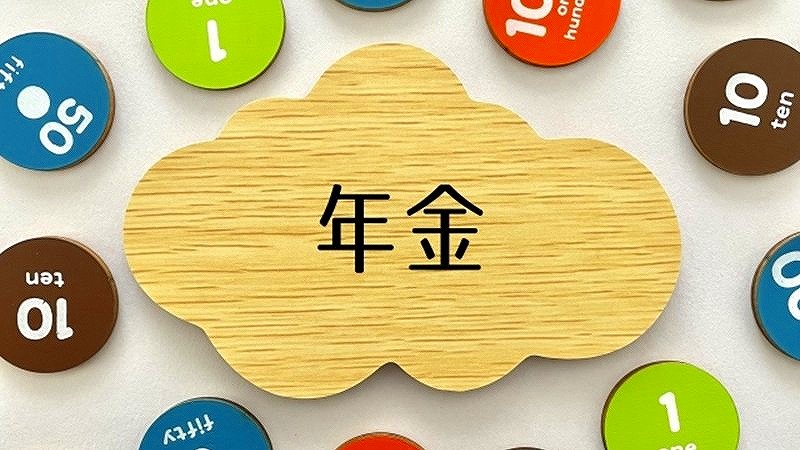
上記の表で分かる通り、退職所得控除額は勤続年数が長いほど増えていきます。
通常は会社を辞めると年数はそれ以上増えませんが、iDeCoで投資をしていると勤続年数(加入期間)としてカウントされます。
なので、会社に勤めなくてもiDeCoで投資しているだけで退職所得控除額が増えていきます。
一時金を受け取る時に、退職所得控除額分の金額は非課税で受け取れますからね。
iDeCoで投資しているだけで退職所得控除額が増えるのは、非常にありがたいですよね。
一時金が退職所得控除額を超えそうな場合は、毎月の投資金額を減らすという方法もあります。
最低投資金額の5000円/月だけ投資しておけば、加入期間としてカウントされます。(要は退職所得控除額を増やせる)
