インデックス投資では、どの口座に投資するかでリターンに差が出ます。
非課税や控除といった制度の違いにより、同じ金額を投資しても最終的な手取り額が変わってきます。
この記事では、毎月の投資金額が決まっている場合に、どの口座から順に使っていくのが良いかを解説します。
ポートフォリオは決まっているけれど、口座の優先順位が分からないという方におすすめです。
本記事では、同じインデックスファンドに投資する前提で比較しています。
iDeCoが最優先
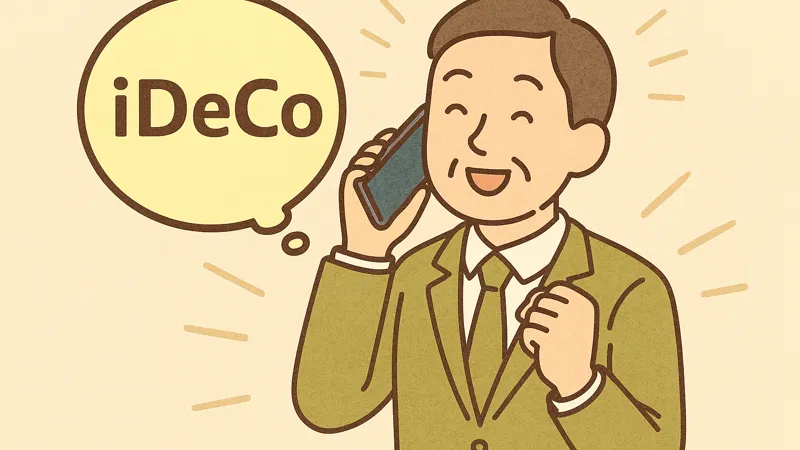
iDeCoは、もっとも節税効果が高い投資口座です。
投資した金額がそのまま所得控除の対象となり、実質的に安く買っているのと同じ効果があります。
毎月の投資上限額は、被保険者種別(第1号、第2号など)によって異なります。
特徴としては、原則として60歳まで引き出すことはできません。
このような制約はあるものの、控除を受けられる人にとっては最優先で使いたい口座です。
所得控除で節税できる
iDeCo最大のメリットは、投資金額の全額が所得控除の対象になることです。
これは、投資に使ったお金がそのまま「課税される所得」から引かれるという仕組みです。
課税される所得が減ると、結果として、所得税と住民税の負担が軽くなります。
仕組みとしてはシンプルですが、他の口座にはない強力な制度です。
どのくらい節税できるか?
iDeCoでどのくらい節税できるかは、所得税と住民税の税率によって決まります。
住民税は全国ほぼ一律で10%、所得税は年収が上がるほど高くなります。
表1:課税所得に対する所得税率(目安)
| 課税所得 | 所得税率 |
| 〜195万円 | 5% |
| 195〜329万円 | 10% |
| 330万円〜 | 20% |
(出典:国税庁)
会社員の方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた金額が、課税所得の目安になります。
たとえば課税所得が400万円なら、所得税20%+住民税10%で、投資金額の30%が節税できます。
仮に毎月2万3000円投資しているのなら、6900円が節税できる計算です。
節税分を再投資する
iDeCoで節税できたお金は、そのまま使わず再投資に回すのが効果的です。
たとえば毎年5万円の節税があるなら、それを新NISAや特定口座で投資することで、さらに資産が増えます。
再投資によって元本が2〜3割増しになれば、受け取り時に税金がかかっても新NISAに負けないでしょう。
逆に、節税で浮いた分を使ってしまうと、新NISAに勝てるかどうかは微妙ですね。
iDeCoが本当に有利になるかは、この再投資をするかどうかにかかっています。
節税できないなら使う必要なし
iDeCoは、所得税や住民税を払っていない人にとってはメリットがありません。
節税の仕組みが効かないため、投資しても税負担が減らず、ただ手数料だけが発生します。
この場合、信託報酬に加えて毎月の口座管理手数料まで引かれてしまい、運用成績を悪化させます。
そのため、節税できない人にとっては、iDeCoは特定口座よりも不利になることがあります。
60歳までに使いたいなら使う必要なし
iDeCoは、原則として60歳になるまで引き出すことができません。
そのため、近いうちにお金を使う予定がある人にとっては、不向きな口座といえます。
たとえ節税メリットがあっても、資金拘束による不便さが上回るケースもあります。
あくまで「老後資金」として割り切れる場合だけ、iDeCoは有効に機能します。
次は新NISA

iDeCoで投資しても、まだ余裕がある場合は新NISAを使います。
年間360万円、合計1,800万円までの非課税枠が用意されており、長期的な資産形成に向いています。
新NISAはつみたて投資枠と成長投資枠に分かれていますが、どちらも非課税期間は無期限です。
いつでも取り崩せるため、老後以外の資金にも使いやすい点がiDeCoとの大きな違いです。
投資する時は所得控除にならない
新NISAでは、投資した金額に対して所得控除は受けられません。
そのため、投資した時点ではiDeCoのような節税効果はありません。
同じ金額を投資する場合、税金が安くなるのはiDeCoだけです。
その点がiDeCoより劣るところです。
受け取り時に非課税になる
新NISAでは、売却時に税金がかかりません。
値上がり益も配当金もすべて非課税で、保有期間に制限もありません。
一度買ってしまえば、将来いつ売っても税金がかからないのが大きなメリットです。
iDeCoの場合は受け取り方によって税金がかかるため、その点ではiDeCoより優れています。
iDeCoで節税して、節税で浮いたお金を新NISAの投資に回す。
これがある意味、最強の投資方法ですね。
最後は特定口座

iDeCoと新NISAで投資しても、まだお金が余っている場合は特定口座を使います。
特定口座には投資上限がなく、いくらでも自由に投資できます。
そのため、新NISAの枠が埋まったあとの受け皿としても十分に活用できます。
また、iDeCoや新NISAの投資資金の一時的な投資先として使うこともできます。(多少リスキーですが)
受け取り時に税金が取られる
特定口座では、売却益や配当に対して20.315%の金融所得課税がかかります。
たとえば10万円の利益が出た場合、約2万円は税金として差し引かれます。
新NISAではこれが非課税になるため、その点では明らかに新NISAの方が優れています。
損益通算や繰越控除が使える
特定口座には、損益通算や繰越控除が使えるというメリットがあります。
たとえば株で損失が出た場合、その年の他の利益と相殺できるため、税金を減らすことができます。
また、損失が出た年に利益がなかったとしても、確定申告をすれば3年間繰り越すことが可能です。
新NISAやiDeCoではこうした仕組みが使えないため、損が出たときのリスク対策としては特定口座の方が優れています。
まとめ:口座の優先順位はこの順番
この記事では、投資口座の優先順位について解説しました。
基本は、iDeCo→新NISA→特定口座の順で使うのが合理的です。
それぞれメリットと制約があるため、特徴を理解して使い分けることが大切です。
どの口座から使うかで、最終的なリターンに差が出てきます。


