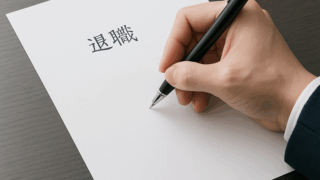前回の記事で試算はしてみたものの、実際に通知書が届くまでは不安でした。
思っていたより高かったらどうしようとヒヤヒヤしていました。
国民健康保険料が前年の所得をもとに4月から変わることを知り、退職2年目の4月に切り替えを決意。
任意継続保険のままだと保険料が高額だったためです。
ただ、当時(令和3年)は「辞めたい」と言えば辞められるような制度ではなく、強制的に資格を喪失させる必要がありました。
そんな時代を経て、実際に切り替えた手続きと保険料の変化について、今回ご紹介していきます。
任意継続から国保に切り替えた理由と方法

退職2年目の保険料試算では、任意継続保険料が年額42万4800円、国保が16万7400円程度と予測されました。
これは大きな差です。
当時、任意継続保険から国保に移るには「未納による強制資格喪失」が唯一の方法でした。
私は楽天銀行の普通預金を定期預金に移して、引き落としを防止。
その後、協会けんぽにより資格喪失が確認されました。
現在では制度が改正され、辞めたい旨を申請するだけで資格喪失が可能です。
- 任意継続保険は年額42万円以上になることもある
- 強制喪失による切り替えは以前は必要だった
- 今は申請で切り替え可能になった
任意継続保険と国保の保険料比較

退職2年目に実際に支払った国民健康保険料は、予想よりも安くなっていました。
以下は、任意継続と国保の違いをまとめた比較表です。
表1:任意継続保険と国民健康保険の保険料比較
| 区分 | 任意継続健康保険 | 国民健康保険 |
| 年額保険料 | 424,800円 | 約150,000円 |
| 計算根拠 | 退職時の標準報酬月額を基に2年固定 | 前年の所得に基づく(退職1年目) |
| 切り替え可能時期 | 最大2年間 | 原則いつでも可能 |
| 扶養の扱い | あり | なし |
| 手続き方法 | 喪失申出または未納による強制喪失 | 市区町村への加入届出 |
(出典:筆者の実体験および全国健康保険協会)
- 年額ベースでは国保の方が圧倒的に安い
- 単身世帯には国保が有利なことが多い
- 手続きの簡便さも現在は改善されている
国民健康保険への切り替え手続きの流れ

任意継続を失効させたあと、協会けんぽから「資格喪失証明書」が送られてきます。
この証明書を持って市民センターに行くと、即日で国保の保険証を交付してもらえました。
任意継続の保険証は無効となるため、協会けんぽに郵送で返却します。
最近ではマイナンバーカードを使って、マイナポータル経由で手続きをすることも可能です。
- 証明書が届いたら速やかに市民センターへ
- 任意継続の保険証は郵送で返却
- マイナポータルでの手続きも可能
実際の通知書でわかった保険料の現実
.png)
前回の試算では、退職2年目の国保は16万7400円と予測していました。
しかし、実際に6月下旬に届いた通知書によると、年額15万円ほどとさらに安くなっていました。
なぜ安くなったのかははっきりしませんが、所得控除や均等割軽減の影響かもしれません。
いずれにせよ、大幅な節約となりました。
- 実際の年額は約15万円だった
- 任意継続との差は約27万円以上
- 軽減制度が適用されていた可能性あり
まとめ:切り替えで保険料が27万円も安くなった

退職後の保険料に悩んでいる方には、任意継続だけでなく国保も選択肢としてしっかり検討していただきたいです。
実際に私が切り替えたことで、年額27万円以上の節約ができました。
手続き自体もそれほど煩雑ではなく、今は制度も改善されてよりスムーズになっています。
家族構成や所得によっては結果が異なるかもしれませんが、試算と通知書を見比べて判断することをおすすめします。
保険料が高すぎるならふるさと納税も活用しよう
退職後の支出が気になるなら、ふるさと納税で家計を少しでも楽にする方法もあります。
私も実際にやっていますが、返礼品で生活費を抑えられるのは助かります。
黒毛和牛やいくらといった高級食材も、実質2000円で手に入るのはありがたいです。
楽天ポイントも付くのでお得感は大きいですよ。
👉 楽天ふるさと納税![]() (PR)
(PR)
※ 制度内容や対象品目は年ごとに変更があるため、寄付前に必ず公式情報をご確認ください。