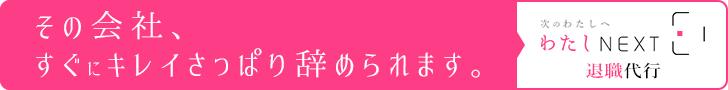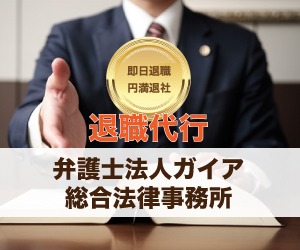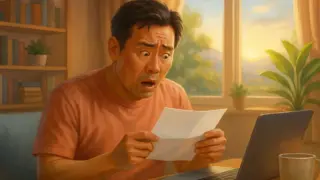
退職直後の健康保険は、会社に勧められるまま任意継続に入りました。
ところが2年目が近づいて、「国保に切り替えた方が安くなるのでは?」と気になり始めました。
この記事では、私の退職2年目の健康保険料を、任意継続と国民健康保険で試算して比較してみます。
退職1年目の健康保険料の高さに驚いている人の参考になるかもしれません。
任意継続の保険料

最初に、任意継続を2年目も続けたときの保険料を整理します。
任意継続の保険料は「退職時の標準報酬月額」に基づいて計算され、原則として2年間は同じです。
ただし、都道府県別の健康保険料率・介護保険料率の変更、任意継続加入中に40歳になって介護保険第2号被保険者に該当する場合など、条件によって金額が変わることがあります。
なので、退職1年目に月額3万5400円だった私の場合、こうした変更がなければ退職2年目も月額3万5400円です。
年額にすると、42万4800円になります。
無職の人間にとっては、なかなか痛い金額ですよね。
- 月額
3万5400円 - 年額
42万4800円
国保の保険料を試算
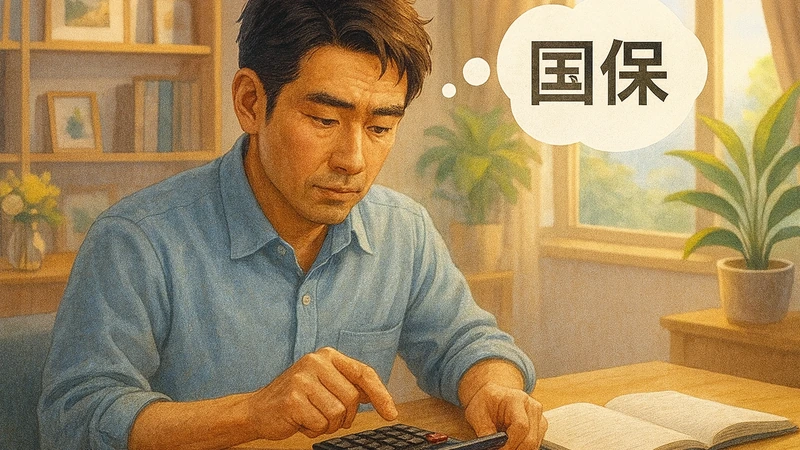
次に、退職2年目の4月から国民健康保険に切り替えた場合の金額を試算します。
先に、この試算の前提条件を書いておきます。
- 世帯構成
実家で親と同居の3人世帯です。 - 後期高齢者医療制度
このうち1人は後期高齢者医療制度の対象で、国民健康保険(国保)の被保険者ではありません。 - 国保の被保険者
国保の被保険者は「私+親1人」の2人として考えます。 - 任意継続の加入状況
現在の任意継続は私1人で加入しており、被扶養者はいません。
国保は請求自体は世帯単位です。
ただこの記事では任意継続と並べて比較したいので、ここでは「私の負担分」に直して計算します。
考え方は次のとおりです。
- 所得割
私の所得だけで計算します。 - 均等割
私1人分を使います。 - 平等割
国保の被保険者が2人なので2で割って私の負担分にします。
計算の手順
国民健康保険料は、基本的に「前年の所得」を基に計算されます。
つまり退職2年目の保険料は、退職1年目の所得を使って決まります。
私の場合は退職1年目に所得がガクッと減ったため、大幅に下がる可能性があります。
国民健康保険料(年額)は、次の3つを足した合計です。
- 所得割
前年の所得に応じて増える部分です。 - 平等割
世帯にかかる固定の部分です。 - 均等割
人数にかかる固定の部分です。
なお、介護分は原則40歳〜64歳が対象なので、年齢によっては不要です。
最初にやるべきことは、「計算」ではなく「数字集め」です。
見る場所は、次の2つだけです。
- 確定申告書
作成中の下書きでもOKです。 - 自治体公式サイト
国民健康保険の「計算方法」または「料率表」を確認します。
確定申告書は、申告書(第一表)の「所得金額等」にある「合計(12)」を見ます。
自治体のページには、医療分・支援分・介護分それぞれについて、次の項目が載っています。
- 所得割率(%)
- 平等割(世帯あたりの定額)
- 均等割(1人あたりの定額)
また、算定基礎額(旧ただし書き所得)の出し方も、自治体のページに書いてあります。
次に、実際の計算の順番は以下のようになります。
- 前年の所得の合計
確定申告書(第一表の「合計(12)」)で確認します。 - 旧ただし書き所得
総所得金額等-基礎控除額(自治体の案内に記載)で出します。 - 所得割
旧ただし書き所得×所得割率(合計)で出します。 - 平等割
平等割(合計)を2人で折半します。 - 均等割
1人あたりの金額をそのまま使います。 - 年額
所得割+平等割(折半後)+均等割(1人分)を合計します。
ここから先は、私の数字を当てはめて順番に計算します。
所得割の計算
まず、確定申告書(下書き)で前年の「所得の合計」を確認します。
見る場所は、申告書(第一表)の「所得金額等」にある「合計(12)」です。
私の退職1年目の所得の合計(申告書第一表の「合計(12)」)は111万円でした。
次に、旧ただし書き所得を出します。
旧ただし書き所得は、総所得金額等から基礎控除額を引いた金額です。
この記事では、基礎控除額を43万円として計算します。
- 旧ただし書き所得
111万円-43万円=68万円
次に、自治体公式サイトの料率表から「所得割率(合計)」を拾います。
私の自治体では、医療分・支援分・介護分を足した所得割率の合計が約13%でした。
なので、この約13%を旧ただし書き所得に掛けます。
- 所得割
68万円×13%=8万8400円
よって、退職2年目の所得割は8万8400円と試算できます。
親の所得がある場合は、世帯としての所得割はその分だけ増えます。
ただこの記事では「私の所得割の金額」を知りたいので、私だけの所得で計算しています。
平等割の折半
平等割は、世帯にかかる固定の金額です。
この金額も自治体公式サイトの料率表に載っています。
私の自治体で、医療分・支援分・介護分を合算した平等割は3万3000円でした。
請求は世帯にまとめて来ますが、この記事では「私の保険料」を出すため、国保の被保険者2人で折半します。
- 平等割(合計)
3万3000円 - 平等割(折半後)
3万3000円÷2=1万6500円
均等割の計算
均等割は、加入者1人ごとにかかる固定の金額です。
この金額も自治体公式サイトの料率表に載っています。
私の自治体で、医療分・支援分・介護分を合算した均等割は4万6000円でした。
- 均等割(1人分)
4万6000円
年額の合計
最後に、所得割+平等割(折半後)+均等割(1人分)を足して、私の年額を出します。
表1:国保(私の負担分)の年額内訳
| 内訳 | 金額 |
| 所得割 | 8万8400円 |
| 平等割(折半後) | 1万6500円 |
| 均等割(1人分) | 4万6000円 |
| 合計(年額) | 15万900円 |
(出典:筆者試算)
月額換算は、15万900円÷12で1万2575円です。
ざっくり言えば、約1万2580円です。
任意継続と国保の差

ここまで出した数字を、そのまま並べて比較します。
今回は「私の保険料」を比べたいので、国保も私の負担分で揃えます。
表2:任意継続と国保の保険料比較
| 保険の種類 | 月額 | 年額 |
| 任意継続健康保険 | 3万5400円 | 42万4800円 |
| 国民健康保険(私の負担分の試算) | 約1万2580円 | 15万900円 |
(出典:筆者試算)
年額の差は、42万4800円-15万900円=27万3900円です。
年約27万3900円の差は、固定費としてかなり大きいです。
これなら多少手続きが面倒でも、切り替える価値は十分ありそうです。
まとめ:国保で年約27万円減

この記事では、私の退職2年目の健康保険料を、任意継続と国民健康保険で試算して比較してみました。
「多少国民健康保険の方が安くなる」と想定はしていましたが、多少どころではなかったですね(笑)
今回の試算どおりなら、退職2年目は国保に切り替えるだけで年約27万円の差が出ます。
この結果を見て、退職2年目は国民健康保険で行くことに決めました。
ただ、国保に切り替えるのは4月からにする予定なので、切り替え方法はこれから調べようと思います。
※本記事は2025年12月時点の情報です。最新情報は公式サイトをご確認ください。