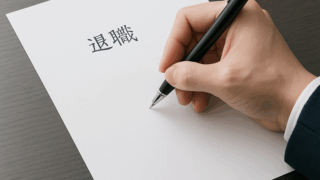退職後に届いた健康保険料の通知を見て、思わず固まりました。
毎月3万超え…。
会社員時代は給料から天引きだったので、健康保険のことなんてほとんど意識していませんでした。
でも、会社を辞めるとそのありがたさに気づくことになります。
この記事では、退職後に選べる健康保険の3つの選択肢と、それぞれの特徴や注意点をわかりやすく解説します。
任意継続・国保・扶養の3択とは

退職後に選べる健康保険の選択肢は、ざっくり言うと3つです。
「任意継続健康保険」「国民健康保険」「誰かの扶養に入る」のどれかになります。
それぞれ保険料の計算方法や扶養の有無などが異なり、自分の状況に合ったものを選ぶ必要があります。
- 任意継続・国保・扶養の3つから選ぶ
- それぞれの仕組みと条件を把握する
- 自分に合った保険を見極める
任意継続健康保険の特徴と落とし穴

任意継続健康保険とは、会社員時代に加入していた健康保険をそのまま最大2年間継続できる制度です。
保険の内容は同じですが、会社の補助がなくなるため保険料は全額自己負担になります。
給料明細を見て「えっ、これの倍!?」と驚いたのは私だけではないはず。
- 退職前の保険をそのまま継続できる
- 保険料は2倍、全額自己負担になる
- 手続きは早めに済ませる
国民健康保険の特徴と比較のコツ

国民健康保険は自営業や無職の人が加入する制度です。
保険料は前年の所得をもとに計算され、扶養の概念がありません。
つまり、家族が多いほど負担も増える可能性があります。
とはいえ、退職2年目など収入が大幅に減った後は、任意継続より安くなるケースもあります。
- 前年の所得で保険料が決まる
- 扶養の概念がなく家族分も加算される
- 減免制度が使える場合もある
扶養に入れるならそれが最安
.png)
誰かの扶養に入れれば、健康保険料の自己負担はゼロになります。
被保険者の収入条件や親族関係などの制限はありますが、可能なら検討すべき選択肢です。
私の場合は扶養してくれる人がいなかったので選べませんでしたが、選べる人は有利です。
- 扶養に入れるなら保険料ゼロ
- 条件に該当するか確認が必要
- 健康保険組合への問い合わせが確実
まとめ:保険料と手続きは退職前に要確認

退職後の健康保険は3つの選択肢がありますが、どれを選ぶかで保険料も手続きも大きく変わります。
私はなんとなく任意継続を選びましたが、実際には事前に確認しておけばよかったと反省しています。
大切なのは「今の自分に合った保険を、損なく選ぶこと」。
そのためには、退職前に役所や協会へ相談するのが一番です。
次のステップを考えるなら転職活動も視野に
健康保険の切り替えは、退職後すぐにやってくる最初の壁です。
でも、選択肢を正しく理解していれば怖くありません。
そして、保険料の負担を減らすという意味では「次の収入源を見つけること」も重要な選択肢のひとつです。
👉 転職、求人情報ならリクルートの転職サイト【リクナビNEXT】![]() (PR)
(PR)
※ 本記事は筆者の実体験と公的機関の情報に基づいており、制度の詳細は最新の情報をご確認ください。