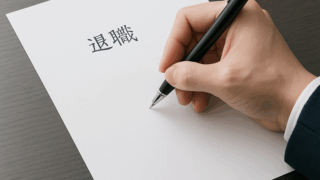会社を辞めた後、健康保険や年金の手続きは話題になりますが、意外と盲点になりやすいのが「住民税」と「失業保険」です。
私も退職したばかりの頃、納付書が突然届いて驚いたことを覚えています。
しかも無職状態での高額請求…
その対処法や仕組みを知っておくだけで、精神的な余裕もかなり違います。
この記事では、退職後に直面する住民税の支払いと、失業保険のリアルな実態について解説します。
自動で届く住民税の納付書と支払い方法

退職後の住民税は、特に手続きをしなくても6月頃に納付書が届きます。
市区町村が前年の所得を基に自動計算して送ってくるので、「どうすればいいの?」と心配する必要はありません。
納付方法は次のとおりです:
- スマホ決済(PayPay、LINE Pay、au PAYなど)
- コンビニ払い(セブンイレブン・ローソンなど)
- 金融機関窓口
納付書は一括払いと4期分割払い(6月・8月・10月・翌年1月)に対応しており、金銭的な余裕や計画に合わせて選べます。
- 納付書は6月に自動で届く
- 前年所得で計算されるため退職1年目は高額になりがち
- スマホ・コンビニ・分割払いで柔軟に対応可能
ふるさと納税で住民税を軽減!

住民税を軽減する方法として真っ先に挙げたいのが「ふるさと納税」。
私も退職前の年に8万円寄付していたおかげで、翌年の住民税からしっかり7万8000円が控除されていました(2000円は自己負担)。
しかも返礼品は黒毛和牛、うなぎ、いくら、ウニなど豪華なラインナップ。
これで実質2000円なら、やらない理由がないですよね。
👉 【返礼品で節税】所得税・住民税を払っているならふるさと納税が超お得!
- 実質2000円で豪華返礼品がもらえる
- 控除額は住民税から直接差し引かれる
- 手続き次第で誰でも簡単に始められる
失業保険の支給にはタイムラグがある

「辞めたらすぐに失業保険がもらえる」と思っていたら要注意です。
実際には申請から2〜3ヶ月後で、しかも求職活動の実績を積まないと受け取れません。
自己都合退職の場合:
- 退職から7日間の待期期間+2〜3ヶ月の給付制限あり
- ハローワークでの求職活動が2回以上必要
申請はハローワークで行い、雇用保険被保険者証、離職票、本人確認書類などを提出します。
- 自己都合退職では支給まで約2〜3ヶ月かかる
- 求職活動の実績が必要(2回以上)
- 申請と手続きはハローワークで行う
まとめ:退職後の住民税と失業保険には備えが必要

退職直後は自由な気分になる一方で、住民税の請求や失業保険の手続きという現実も待っています。
特に住民税は、前年度の収入がベースになるため、無職でも高額請求が来る可能性がある点に注意が必要です。
一方で、ふるさと納税や分割払い、スマホ納付など、負担を軽減する手段もあります。
失業保険も条件を満たせばしっかり支給される制度です。
退職後のリアルを知っておくことで、金銭面の不安を減らし、次のステップに備えることができます。
次の一歩を探そう|転職活動は今すぐスタート
住民税や失業保険の手続きを済ませたら、次は次の仕事をどうするかも考えるタイミングです。
退職後の空白期間をムダにしないためにも、まずは求人をチェックしてみませんか?
👉 転職、求人情報ならリクルートの転職サイト【リクナビNEXT】![]() (PR)
(PR)
※ 求職活動の証明には応募・相談実績が必要になる場合があります。転職サイトの活用も立派な実績になります。