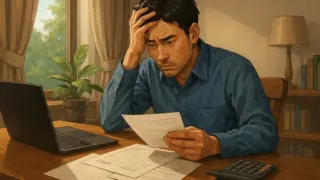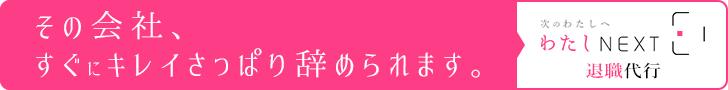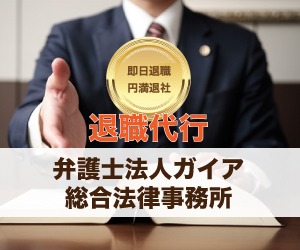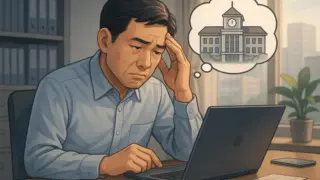退職金は、会社の中でもあまりオープンに語られないテーマだと思います。
そのせいか、「自分の退職金がどういう仕組みなのか」をよく分からないまま過ごしている人も多いのではないでしょうか。
この記事では、退職金の主なパターンと、退職前に押さえておきたいポイントを書いていきます。
これから会社を辞めようと思っている人の参考になるかもしれません。
退職金制度の概要
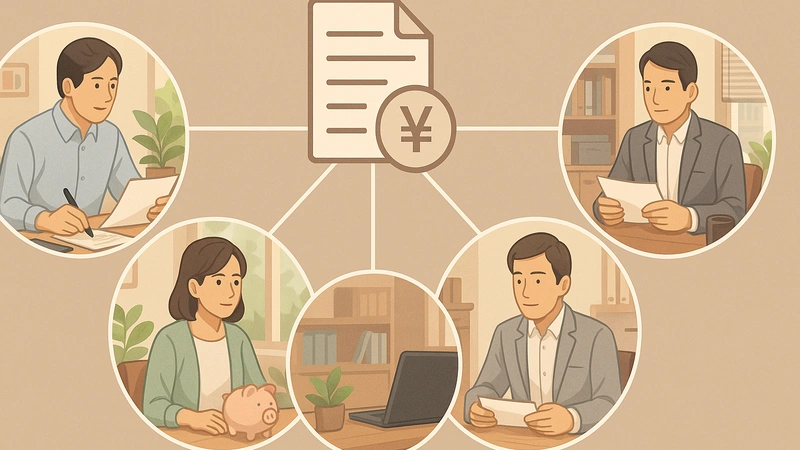
会社を辞めるときに受け取るお金には、いくつかパターンがあります。
ここでは、「どこから・どんな形で出てくるお金なのか」をざっくり整理しておきます。
会社独自の退職金
会社が自前で積み立てて、退職した社員に直接支払う退職金です。
- 支給ルール
会社独自の退職金(退職一時金)として、就業規則や退職金規程の退職金テーブルに従って金額が決まる。 - 受け取り方
退職後に会社から本人の口座へ一括振り込まれる。 - 税金の扱い
退職所得として源泉徴収され、「退職所得の源泉徴収票」が発行される。
企業年金
退職一時金とは別に、60歳以降の上乗せ年金として用意されているお金です。
- 代表的な制度
企業年金(確定給付企業年金など)のように、将来の給付額があらかじめ決まっているタイプ。 - 受け取り方
退職後に届く案内に従って、「年金」か「一時金と年金」を自分で選ぶ。 - 早期退職との関係
退職直後に使える一時金部分と、60歳以降の年金部分の配分は制度ごとに違う。
企業型DC
企業型DC(企業型確定拠出年金)は、会社が掛金を出し、自分で運用商品を選ぶタイプの年金です。掛金の額は決まっていますが、将来いくら受け取れるかは運用次第です。
- お金の性格
企業型DC(企業型確定拠出年金)で積み立てたお金は、原則60歳になるまで引き出せない老後資金で、退職時の現金退職金にはならない。 - 退職時の手続き
退職したら、企業型DC(企業型確定拠出年金)の残高を転職先の企業型DCや個人型iDeCoなどに自分で移換する必要がある。 - 放置リスク
移換せず放置すると自動移換され、運用が止まったり手数料だけ差し引かれることがある。
企業型DCやiDeCoの仕組みや受け取り方の全体像は、厚生労働省やiDeCo公式サイトの制度解説も確認しておくと安心です。
共済型退職金
中退共や特定退職金共済などの「共済型退職金」は、会社の外にある共済に積み立てておき、退職時にそこから支払われる退職金です。
- 代表的な制度
中退共や特定退職金共済などの共済型退職金。 - 支給の流れ
会社が退職の届出をし、本人が中退共や特定退職金共済などからもらった請求書を記入して郵送すると、自分の口座に振り込まれる。 - 総務のひと言の意味
「退職金は中退共に請求してください」と言われたら、この共済型退職金で受け取るパターン。
中退共そのものの仕組みや加入条件、掛金の扱いなどは、公的な制度解説を一度読んでおくとイメージが掴みやすくなります。
厚生労働省「中小企業退職金共済制度(中退共制度)」/中退共公式サイト
公務員の退職手当
公務員の退職金は、公務員の退職手当として別の制度になっています。最終の俸給月額や勤続年数、退職理由などに応じて退職手当の額が決まります。
- 計算のイメージ
俸給月額に勤続年数・退職理由ごとの支給率を掛けて退職手当を出す方式。 - 受け取り方
所属庁の人事・総務から案内されたとおりに請求書等を提出し、一時金や退職年金として支給される。 - 実務上のポイント
民間のように中退共や企業年金基金に自分で問い合わせるのではなく、公務員の退職手当として所属先の案内に沿って手続きする。
国家公務員の退職手当の算定式や支給率の詳細は、人事院が公表している退職手当制度の概要で確認できます。
退職前にやっておくこと
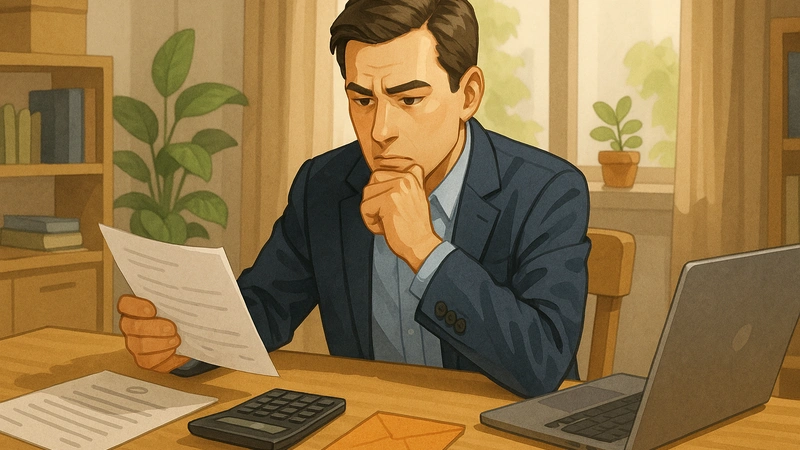
退職前にやっておくと後で効いてくる、「退職金まわりの下準備」を3つだけ挙げておきます。
退職金制度を調べる
私の会社は中退共に積み立てをしていたようですが、私はそんなことは全く知りませんでしたね。
総務から「退職金は中退共に請求してください」と言われても、「何それ?」みたいな感じでした。
そういう人もけっこういるんじゃないですかね?
退職金の仕組みを細かく覚える必要はありませんが、「どこを見ればいいか」くらいは、次の3つだけ押さえておくと楽です。
- 就業規則・退職金規程(退職金/退職一時金の欄)
- 給与明細・社内ポータル(企業年金/企業型DCの有無)
- 総務への一言確認(うちの退職金の仕組み)
退職金の金額を把握しておく
そんな感じだったので、私は辞めることが決まってから、総務の説明で初めて退職金の金額を知りました。
今から思えば、これは相当無謀でしたね。
退職金の金額は、辞める前に把握しておいた方がよいと思います。
というのも、退職金は辞めてからの貴重な収入だからです。
会社を辞めてからの生活設計をするうえで、退職金を計算に入れるかどうかで、かなり話が変わってきます。
なので、これから辞める人は、先に退職金の金額を調べてからにした方がよいでしょう。
というか、辞める気がない人でも、「今辞めたらいくらもらえるか」と「定年まで勤めたらいくらになるか」くらいは押さえておいた方がいいですね。
ただ、総務にしつこく聞くと、「コイツひょっとして辞める気なんじゃないだろうな」と疑われそうですが(笑)
源泉徴収票は保管しておく
退職金をもらうと源泉徴収票がもらえますが、これは大切に保管しておいた方がいいですね。
というのも、iDeCoで一時金を請求するときに、コピーが必要になるからです。
細かくは書きませんが、源泉徴収票のコピーがないと、税法上の優遇措置が受けられない可能性があります。
私は確定申告したあとに捨ててしまいましたが、それを知って、慌てて中退共に再発行してもらいました。
ただ、私の場合は会社を辞めてからiDeCoを始めたので、あまり関係なさそうですが……。
いずれにしろ、iDeCoを利用している人は、手元に残しておく方がよいでしょう。
なお、中退共の源泉徴収票は、いつまでも再発行してもらえるわけではありません。
まとめ:退職前の要点

この記事では、退職金の主なパターンと、退職前に押さえておきたいポイントを書きました。
会社を辞めてから困らないように、退職金の金額を調べてから「辞める」と言いましょう。
あんまり少ないことが分かってしまうと、辞められなくなってしまうかもしれませんが(笑)
また、iDeCoをやっているなら、退職金の源泉徴収票は大切に保管しておきましょう。
※ 本記事は2025年12月時点の情報です。最新情報は公式サイトをご確認ください。