iDeCoは、所得控除で節税できるならなるべく使いたい制度です。
自分も2022年から始めています。
iDeCoを始める時はまず金融機関を選ばなければいけませんが、金融機関選びは非常に重要です。
変な金融機関を選んでしまうと、あとあと後悔することになります。
ということで、今回はiDeCo口座を申し込む金融機関の選び方について書いていきます。
1番重要なのは運営管理手数料の安さ
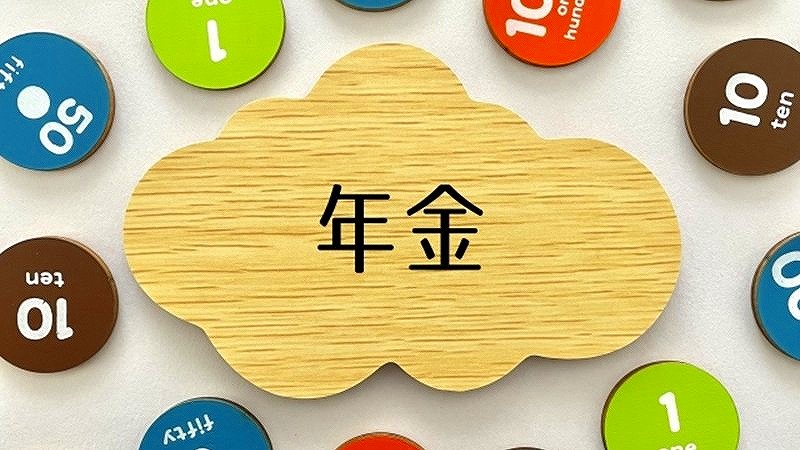
運営管理手数料とは、金融機関がiDeCo口座を管理するための手数料です。
一度口座を作ると、口座がなくなるまで毎月支払う必要があります。
運営管理手数料が無料の金融機関を選ぶ
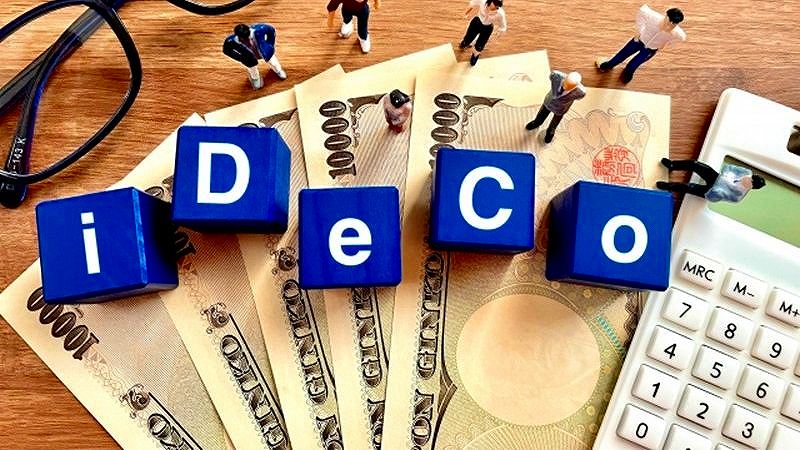
運営管理手数料は、金融機関によって異なります。
ほとんどの金融機関は有料ですが、ごく一部の金融機関は無料です。
どちらもやっていることは同じなので、当然ですが無料の金融機関を選ぶ方が良いに決まっています。
iDeCo口座は、原則として60歳までは持ち続ける必要がありますからね。
運営管理手数料が有料の金融機関を選ぶと、口座がなくなるまで毎月手数料を取られる羽目になってしまいます。
「人の年金の口座から金をかすめ取るんじゃねえ」という感じですよね。
候補となる金融機関は17社

運営管理手数料が無料の金融機関を探すには、下記のサイトが非常に便利です。
上記のサイトの「運用期間中かかる費用(毎月)」の「積立を行う場合」が171円以下、「積立を行わない場合」が66円以下の金融機関が運営管理手数料無料です。 (ここ重要)
この171円と66円は他でかかる手数料なので、気にする必要はありません。
2025年3月現在では、運営管理手数料が無料の金融機関は全部で20社あります。
その中から、資産〇万円以上という条件付きの金融機関は面倒くさいので除外します。
すると、候補となる金融機関は17社に絞られます。
- イオン銀行
- 岡三証券
- さわかみ投信
- 住友生命保険
- 大和証券
- 日本生命保険
- 野村證券
- 松井証券
- マネックス証券
- 三井住友銀行(みらいプロジェクト)
- 三菱UFJ eスマート証券
- 楽天証券
- りそな銀行
- auアセットマネジメント
- SBI証券(セレクトプラン)
- SMBC日興証券
- 第一生命保険
上記以外の金融機関では、iDeCo口座を作る価値がないと言って良いでしょう。
次に重要なのは商品の質
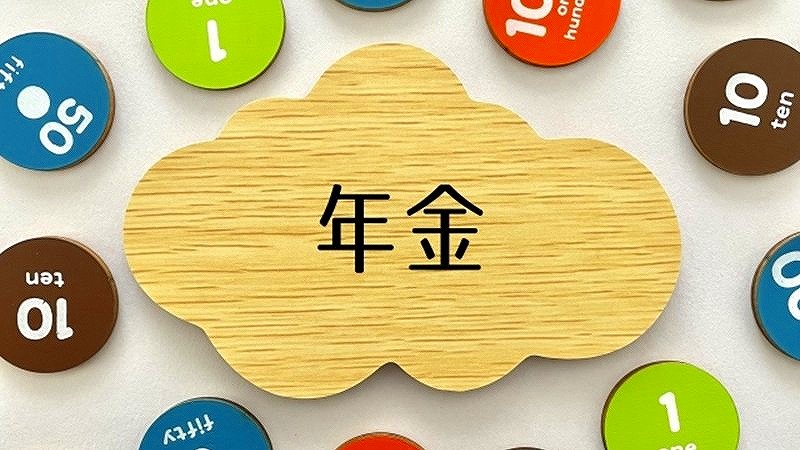
候補として残った金融機関は、17社あります。
問題は、その中からどの金融機関を選ぶかです。
その決め手となるのは、商品ラインナップです。
17社の商品ラインナップ
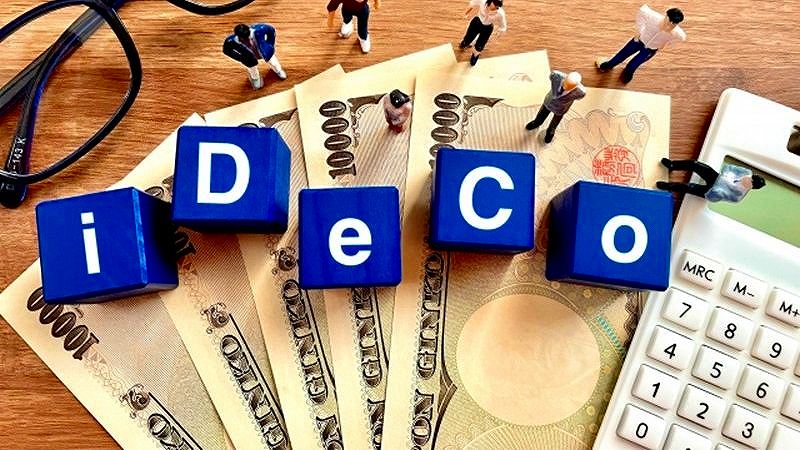
候補として残った金融機関の商品ラインナップは、下記になります。
こちらもiDeCoナビから引用します。
買いたい商品がある金融機関を選ぶ

あとは、買いたい商品のある金融機関を選べばOKです。
ここは時間を掛けて、じっくり選びたいですね。
買いたい商品がない金融機関を選んでしまうと、あとあと後悔することになります。
あとからでも金融機関の変更はできますが、手間がかかる上に手数料まで取られることもあるのであまりやりたくありません。
17社の「eMAXIS Simシリーズ」の本数
参考までに、17社の商品ラインナップにみんな大好き「eMAXIS Simシリーズ」が何本あるか調べてみます。
- 松井証券:13
- SBI証券(セレクトプラン):8
- auアセットマネジメント:7
- マネックス証券:6
- SMBC日興証券:1
- その他:0
松井証券が群を抜いて多いですね。
「eMAXIS Simシリーズ」が多ければ良いというわけではないですが、参考にはなるでしょう。
個人的に使っているのは松井証券
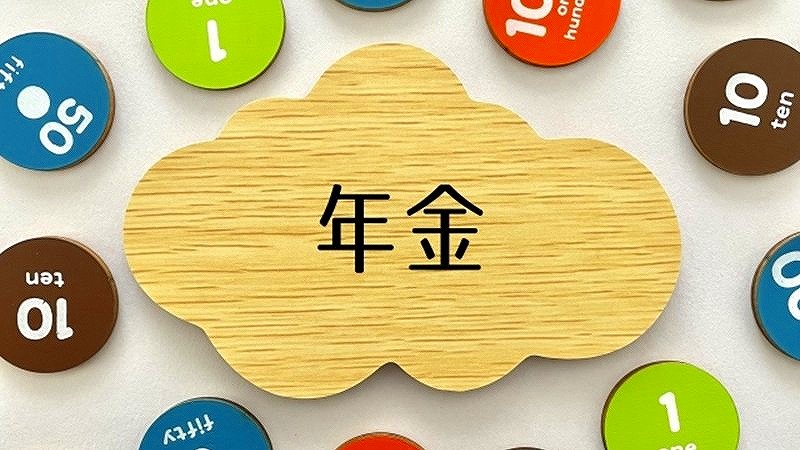
個人的には、iDeCo口座は松井証券を使っています。
運営管理手数料が無料なのは当然として、その他の理由は下記の2つです。
- 商品ラインナップが最高
- 投資信託の保有でポイントが貯まる
商品ラインナップが最高
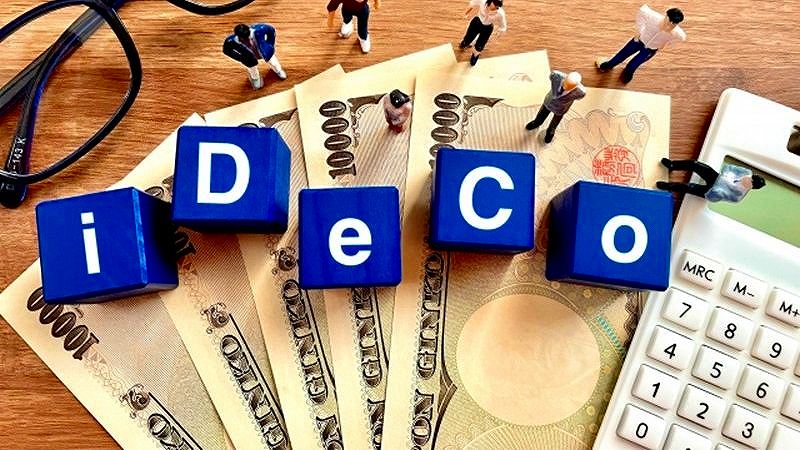
個人的には、松井証券の商品ラインナップは最高です。
自分の買いたいインデックスファンドが全て揃っています。
- eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
- eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
- eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
- eMAXIS Slim 国内債券インデックス
- eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
- iFree 新興国債券インデックス
- eMAXIS Slim 国内リートインデックス
- eMAXIS Slim 先進国リートインデックス
これだけあれば、もう十分ですね。
何も言うことはありません。
iDeCo口座だけで、8資産のインデックス投資が完結します。
と言うかね、本当にiDeCoで年金を国民に作らせてくれようと考えているのは松井証券だけだと思いますよ。
他の金融機関では、8資産でポートフォリオを組んでいる人には当然のラインナップが揃いませんからね。
もう「アホか」と言いたくなります。
松井証券のiDeCo口座の申し込みは、モッピーからがおススメです。
iDeCoの投資信託でポイントが貯まる

松井証券では、iDeCoの投資信託の保有でポイントが貯まります。
iDeCoはポイント付与の対象外になる金融機関がほとんどなので、これは嬉しいですね。
貯まったポイントは、投資信託の積立や他のポイント(PayPayポイントやdポイントなど)と交換できます。
SBI証券も悪くない
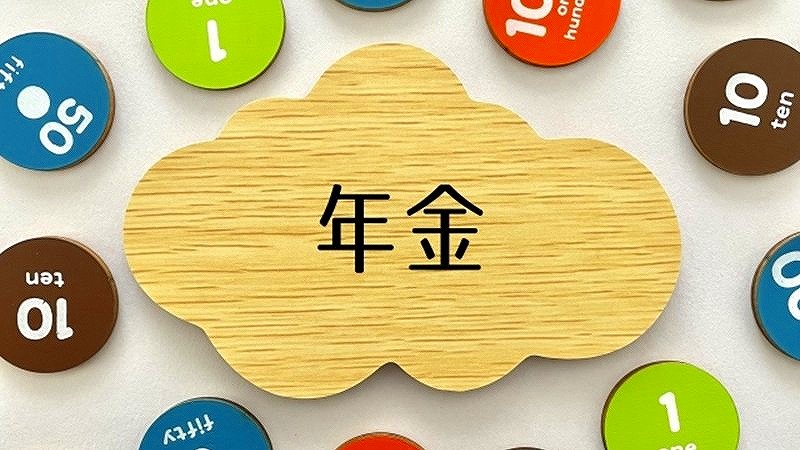
SBI証券も、iDeCoの商品ラインナップが良いですね。
「eMAXIS Slimシリーズ」も8本ありますし。
ただ、リートに「eMAXIS Slim」がないのが少し残念ですけどね。
「eMAXIS Slim」のリートは比較的新しいので、入れらなかったのかもしれませんが。
まあ、代わりにあるリートのインデックスファンドも悪くないので十分と言えば十分ですけどね。
個人的には、松井証券の方が良いと思いますけど。
SBI証券のiDeCo口座の申し込みは、モッピーからがおススメです。

