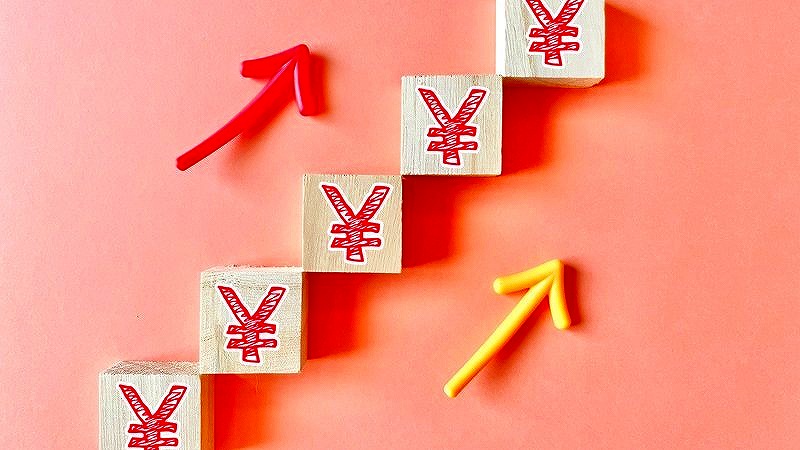楽ラップは、楽天証券のロボアドです。
お金を入れるだけで、勝手に資産運用してくれます。
なので、自分で投資するのが面倒くさいという人にはピッタリのサービスです。
今時銀行預金していても、超低金利でお金が全然増えませんからね。
それならば、多少リスクを取っても投資でお金を増やすという考え方もあります。
ただ、楽ラップは手数料がかかります。
なので、できるだけ自分でインデックス投資をした方が良いとは思いますが…。
ということで、今回は「自分で投資するのが面倒なら楽ラップを使うのも悪くない」を書いていきます。
とにかく楽

楽ラップの良いところは、とにかく楽なところです。
投資のことなど何も知らなくても、楽ラップが勝手に資産運用してくれます。
お金を入れるだけでOK

楽ラップでやることと言えば、お金を入れることくらいです。
1万円からスタートでき、積立したければ毎月の積立も1万円以上で設定できます。
それだけやっておけば、あとは楽ラップの方で資産運用してくれます。
ただし、楽ラップを申し込むには楽天証券で口座開設する必要があります。
資産配分を考える必要がない

インデックス投資で1番重要かつ難しいのは、間違いなく資産配分を決めることです。
資産配分は、投資成績に大きな影響を与えます。
しかし、将来的に何が上がって何が下がるのかが誰にも分からないため正解が分かりません。
そのため、インデックス投資をしている人は誰でも資産配分で悩みます。
その点、楽ラップでは最初に運用コース診断をするだけでOKです。
その結果を見て、ロボアドバイザーが運用コースを提案してくれます。
ちなみに、運用コースは下記の9つがあります。
- 保守型
とにかく「慎重派」だという人向けの運用コース
- やや保守型(DRCあり or なし)
基本は慎重だけど、攻めの姿勢も忘れない人向けの運用コース
- やや積極型(DRCあり or なし)
資産の保全を図りつつ、攻めたい人向けの運用コース - 積極型(DRCあり or なし)
リスクをある程度見込んで収益性を追求したい人向けの運用コース - かなり積極型(DRCあり or なし)
とことん収益性を追求していきたい人向けの運用コース
保守型以外は、DRCあり、なしに分かれています。
DRC機能とは、下落ショック軽減機能のことです。
不安定な相場環境下で、値動きのブレを軽減したい人のための機能です。
買う商品も考える必要がない

インデックス投資をする時は、資産配分を決めたあとに買う投資信託を決めます。
投資信託は商品数が多いので、自分で選ぶとけっこう悩みます。
その点、楽ラップでは運用を始めると資産配分通りに投資信託を選んで買ってくれます。
なので、どの投資信託を買うかなどと悩む必要が全くありません。
メンテも勝手にやってくれる

インデックス投資はそれほど手間がかかりませんが、多少のメンテは必要になります。
その点、楽ラップは放っておいても勝手にメンテしてくれます。
主なメンテは下記です。
- 資産配分の見直し
市況を見て資産配分を見直す。3ヶ月に1回実施。 - 投資信託の見直し
市況を見て資産ごとの投資信託を見直す。3ヶ月に1回実施。
- リバランス
資産配分が大きく崩れている場合に元の資産配分に戻す。1ヶ月に1回実施。 - DRC機能の発動
株式市場の値動きが激しくなった場合に株式の配分を下げ、債券の配分を増やす。不定期。 - DRC機能の解除
相場が落ち着いたら通常の配分に戻す。不定期。
定期的にやるのは、資産配分・投資信託の見直しとリバランスです。
DRC機能については、DRCありの運用コースを選んだ時のみ発動・解除します。
過去の運用成績

楽ラップを始めようと思っている人が気になるのは、どれだけ儲かるかだと思います。
いくら楽でも、儲からなければお金を入れる意味がありませんからね。
ということで、どれだけ儲かるかを調べたいところですが今後のことは誰にも分かりません。
なので、過去5年間を調べていきます。
運用コースごとに、過去5年間の騰落率(5年前よりどれだけ増えたか)をまとめてみます。
| 運用コース | 5年間騰落率 | 年平均換算 |
| 保守型 | 15.82% | 2.98% |
| やや保守型(DRCなし) | 27.63% | 5.00% |
| やや保守型(DRCあり) | 19.55% | 3.63% |
| やや積極型(DRCなし) | 39.57% | 6.89% |
| やや積極型(DRCあり) | 25.49% | 4.64% |
| 積極型(DRCなし) | 50.66% | 8.54% |
| 積極型(DRCあり) | 34.92% | 6.17% |
| かなり積極型(DRCなし) | 62.96% | 10.26% |
| かなり積極型(DRCあり) | 45.06% | 7.72% |
※2024年2月29日時点
DRCありよりDRCなしの方が騰落率が高いのは、それだけリスクを取っているので当然だと言えます。
それよりも注目したいのは、1番手堅い保守型でも銀行預金するよりずっと良い結果が出ていることです。
これなら少額でもやってみようと思う人もいるかもしれませんね。
ただ、この数字は税金、手数料等を考慮していないので実質的な投資成果を示すものではありません。
手数料は取られる

楽ラップは便利ですが、もちろんタダで使えるわけではありません。
手数料がかかります。
手数料コースは2種類あり、どちらかを選択します。
- 固定報酬型
毎月、資産運用残高に一定の比率をかけた固定報酬を支払うコース。
固定報酬:最大年率0.715% - 成功報酬併行型
固定報酬に加え、一定期間の運用成果に応じた成果報酬を支払うコース。
固定報酬:最大年率0.605%
成功報酬:運用益の5.5%
固定報酬が最大年率となっているのは、運用資産の時価評価額が増えるほど率が下がっていくからです。
問題はどちらが得なのかですが、1年間の収益率が2%を超えてくると固定報酬型の方がお得になるようです。
それならば、どの運用コースを選んでも固定報酬型の方がお得になりそうですが…。
ただ、先のことは誰にも分かりません。
お金関係の良いサイト

お金関係で、個人的に良いと思うサイトを箇条書きしていきます。
個人的に良いと思う銀行は1つだけです。
- 楽天銀行
楽天証券との口座連携(マネーブリッジ)で金利アップ。銀行は楽天銀行だけで十分。
個人的に良いと思うクレジットカードは3つです。
- 楽天カード
普段使い。基本は楽天ペイにチャージして使う。楽天ポイントが貯まる。年会費無料。 - 三井住友カード(NL)
SBI証券のクレカ積立で使える。年会費無料。クレカ積立以外で年間10万円利用しないとクレカ積立のポイントがもらえないので10万円だけ使う。 - PayPayカード
国民年金納付で1%のポイント還元があるので、その時だけ使う。年会費無料。
個人的に良いと思う証券会社は3つです。
個人的に良いと思うポイントサイトは2つです。
その他、便利だと思うサイトは下記です。
- myINDEX 資産配分ツール
各資産のリターンの確認に便利。インデックス投資をするならマスト。 - 「インデックスファンド」コスト比較ランキング
コストの安いインデックスファンドが分かる。インデックス投資をするならマスト。 - ねんきんネット
自分の年金記録を確認するのに必須。 - マネーフォワードME
自分の資産がどのくらいあるのか分かる。有料なら5つ以上の金融機関を登録できるが、金融機関を整理すれば無料でも十分使える。
お金関係のAmazonランキングは下記です。
ということで、今回は終わりにします。