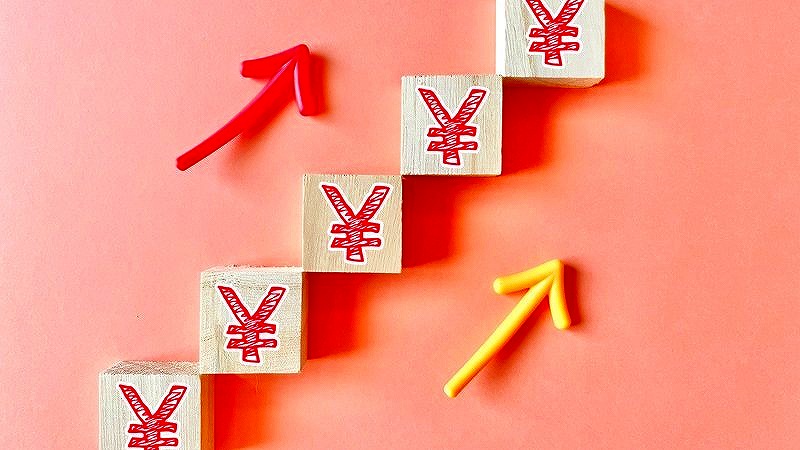インデックス投資をしていると、アセットアロケーションは悩みの種です。
そもそも正解がないので、どうすれば良いのかさっぱり分かりません。
なので、個人的にはアセットアロケーション作成は楽ラップにお任せしています。
楽ラップはポートフォリオをバッチリ公開しているので、誰でも確認できます。
あとはそれを見ながら同じようにすればOK、というわけです。
ということで、今回は「楽ラップとほとんど同じポートフォリオを作る方法」を書いていきます。
楽ラップとは

楽ラップは、楽天証券のロボアドです。
「ロボアドバイザー(通称:ロボアド)」は、いくつかの質問に答えることで、その人に合ったポートフォリオや投資信託を提案してくれるサービスの総称です。
楽ラップは、ロボアドバイザーによる運用コースの提案に加え、その後の資産運用まで自動で行うサービスとして2016年7月にサービスを開始しました。
要は、お金を入れるだけでロボアドが勝手に資産運用してくれます。
手数料は多少かかりますが、自分は何もする必要がありません。
なので、自分で投資したくない人にはピッタリのサービスです。
参考にする運用コースを決める

楽ラップには、大きく分けて5つの運用コースがあります。
- 保守型
とにかく「慎重派」だという方のための運用コース。
5年間騰落率:16.52%
- やや保守型
基本は慎重だけど、攻めの姿勢も忘れない方のための運用コース。
5年間騰落率:28.20%
- やや積極型
資産の保全を図りつつ、攻めたい方のための運用コース。
5年間騰落率:40.10% - 積極型
リスクをある程度見込んで収益性を追求したい方のための運用コース。
5年間騰落率:51.11% - かなり積極型
とことん収益性を追求していきたい方のための運用コース。
5年間騰落率:63.37%
※2024年1月末時点
下に行くほど、大きなリスクを取って大きなリターンを取りに行くコースになっています。
5年間騰落率とは、過去5年間でどのくらい増えたかを表したものです。
けっこう高いですが、税金、手数料等を考慮していないので本当はもう少し下がります。
まずは、この中から自分の投資方針に近いものを選びます。
アセットアロケーションの確認

参考にする運用コースが決まったら、アセットアロケーション(資産配分)を確認します。
まず、参考にする運用コースのマンスリーレポートを開きます。
マンスリーレポートとは、楽ラップから毎月発行されるレポートのことです。
開くのは、下記のいずれかになります。
マンスリーレポートを開くと、「アセットクラス・銘柄の基本構成比」という項目があります。
その下の表から「サブアセットクラス」という列を探します。
その列を見ていくと8資産が並んでおり、「当月末」の割合が書かれています。
それが、楽ラップのアセットアロケーション(資産配分)になります。
先進国株式と先進国債券は為替ヘッジの有無で2行に分かれていますが、足せば良いと思います。
買うのは為替ヘッジなしの投資信託だけで十分だと、個人的には思います。
ポートフォリオの作成

次に、実際に買う商品を決めます。
楽ラップのポートフォリオは、先ほどの表の「組入銘柄」に載っています。
しかし、楽ラップでは楽ラップ専用のファンドを使っているため同じものは購入できません。
なので、代わりの投資信託を探します。
個人的には、下記の投資信託がいいと思いますけどね。
- 国内株式:eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
- 先進国株式:eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
- 新興国株式:eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
- 国内債券:eMAXIS Slim 国内債券インデックス
- 先進国債券:eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
- 新興国債券:iFree 新興国債券インデックス
- 国内リート:eMAXIS Slim 国内リートインデックス
- 先進国リート:eMAXIS Slim 先進国リートインデックス
まあ、買う商品は自己責任なので他を選んでもいいですが…。
資産ごとに買う投資信託が決まれば、ポートフォリオの完成になります。
あとは。アセットアロケーションの割合通りに投資信託を購入していくだけです。
メンテ方法

楽ラップでは、一定の期間ごとにアセットアロケーションの見直しがあります。
楽ラップでは、基本となる長期的な見通しに基づく資産配分(戦略的資産配分)を年に1度見直します。
さらに、中期的な見通しでの資産配分(動的資産配分)の見直しも3ヵ月に1度行います。
現在のところ、中期的な見直しは1月・4月・7月・10月に実施しています。
アセットアロケーションがどう変更されたかを知るには、マンスリーレポートで確認します。
「当月末」と「前月末」の比率を比較すれば、変更箇所が分かります。
それに従って、自分のアセットアロケーションも変更すればOKです。
現在のところ、マンスリーレポートは翌月の15~20日頃に発行されています。
なので、それまでは細かいアセットアロケーションの変更は確認できません。
注意点としては、マンスリーレポートの過去データは見れないことです。
なので、残しておく場合はPCに保存しておく必要があります。
お金関係の良いサイト

お金関係で、個人的に良いと思うサイトを箇条書きしていきます。
個人的に良いと思う銀行は1つだけです。
- 楽天銀行
楽天証券との口座連携(マネーブリッジ)で金利アップ。銀行は楽天銀行だけで十分。
個人的に良いと思うクレジットカードは3つです。
- 楽天カード
普段使い。基本は楽天ペイにチャージして使う。楽天ポイントが貯まる。年会費無料。 - 三井住友カード(NL)
SBI証券のクレカ積立で使える。年会費無料。クレカ積立以外で年間10万円利用しないとクレカ積立のポイントがもらえないので10万円だけ使う。 - PayPayカード
国民年金納付で1%のポイント還元があるので、その時だけ使う。年会費無料。
個人的に良いと思う証券会社は3つです。
個人的に良いと思うポイントサイトは2つです。
その他、便利だと思うサイトは下記です。
- myINDEX 資産配分ツール
各資産のリターンの確認に便利。インデックス投資をするならマスト。 - 「インデックスファンド」コスト比較ランキング
コストの安いインデックスファンドが分かる。インデックス投資をするならマスト。 - ねんきんネット
自分の年金記録を確認するのに必須。 - マネーフォワードME
自分の資産がどのくらいあるのか分かる。有料なら5つ以上の金融機関を登録できるが、金融機関を整理すれば無料でも十分使える。
お金関係のAmazonランキングは下記です。
ということで、今回は終わりにします。